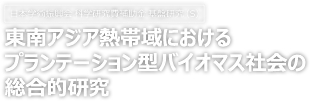アブラヤシの故地を巡るー 西アフリカ、ギニア紀行 石川 登
アブラヤシの故地を巡る― 西アフリカ、ギニア紀行
石川 登(京都大学 東南アジア研究所)私たちの調査地であるサラワク州でも日常的なランドスケープとなりつつあるアブラヤシ注1の原産地はアフリカである。故地を離れて東南アジア島嶼部で拡大した商品作物という意味で、ゴムと同様にたいへん興味深い植物だ。現在、アブラヤシは、プランテーションというかたちをとって東南アジア島嶼部の社会や生態系に大きな影響を与えている。アブラヤシの故地をアフリカ大陸に探る ― このような目的をもった西アフリカ調査の道すがら考えたことを以下に記してみたい。去る2011年8月12日から21日まで、京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科の山越言さん(霊長類学・アフリカ地域研究)、同地域研究統合情報センターの柳沢雅之さん(農業生態学・ベトナム地域研究)、平井將公さん(生態史・アフリカ地域研究)とともにギニアとセネガルを旅する機会を得た。旅の詳細やフィールド情報を記す紙幅はないが、以下では、三人の同僚との分野を越えた論壇風発を通して得た、自分のなかでの小さな発見をいくつか紹介したい。

 私たちがボルネオで接している森林産物は、その多くが世界的な市場ネットワークのなかで商品として流通してきた。アブラヤシ、木材、ゴム、ココ椰子、エンカバン、籐、ジュルトン、ダマール、グッタペルカ、燕の巣など森林産物が欧米、中東、極東へと運ばれてきた。プナンやカヤン、そしてイバンの人々が採集した森林資源は、大陸を結ぶ海底ケーブル材として、欧州戦時下の手榴弾用バスケットや馬具のなめし剤として、さらには儀礼の際に焚きしめる香や香港の高級レストランの食材として海をわたった。これらのボルネオの森林資源の交易ネットワークに比して、より「リージョナル」であるのが西アフリカの森林産物であるといえるのではないか。象牙やコパールなどを除けば、世界大のネットワークにのって大いに交易された森林産物は東南アジアに比べれば少ないようだ。コラの実もコカ・コーラの原料とされたことはつとに知られているが、その主な交易圏はアフリカの域内である。なぜ熱帯アフリカの森林産物は、世界商品にならなかったのか。ひるがえって、なぜ東南アジア島嶼部のそれはシンガポールやロンドン市場と直結し、世界大の商品となったのか。このような複眼的な問いを立て解をえるためには、アフリカとアジアを歩きまわるしかないようだ。
現在、西アフリカでもプランテーション型のアブラヤシ植栽が進んでいる。いままで触れてきた伝統的なアブラヤシに対して、拡大中のものはマレーシアやインドネシアで目にする短躯多葉なハイブリッド種である。ギニアで訪れたプランテーションは、まさに私たちがマレーシアで馴染んでいるものである。これらの椰子から生産される油は、ローカル種からできる食用油とは異なる生産システムと流通経路を形成している。ギニアでのアブラヤシ・プランテーション開発は、その緒についたばかりであり、東南アジアのそれと比して規模も小さい。この産業の未来は、マレーシアやインドネシアが経験したように労働の組織化をどう行うかにかかっている。マレーシアのように国外の低賃金労働者を動員できるのか。はたまたインドネシアのように小農を組みこんだ生産システムが生まれる可能性があるのか。注目していきたいところである。
私たちがボルネオで接している森林産物は、その多くが世界的な市場ネットワークのなかで商品として流通してきた。アブラヤシ、木材、ゴム、ココ椰子、エンカバン、籐、ジュルトン、ダマール、グッタペルカ、燕の巣など森林産物が欧米、中東、極東へと運ばれてきた。プナンやカヤン、そしてイバンの人々が採集した森林資源は、大陸を結ぶ海底ケーブル材として、欧州戦時下の手榴弾用バスケットや馬具のなめし剤として、さらには儀礼の際に焚きしめる香や香港の高級レストランの食材として海をわたった。これらのボルネオの森林資源の交易ネットワークに比して、より「リージョナル」であるのが西アフリカの森林産物であるといえるのではないか。象牙やコパールなどを除けば、世界大のネットワークにのって大いに交易された森林産物は東南アジアに比べれば少ないようだ。コラの実もコカ・コーラの原料とされたことはつとに知られているが、その主な交易圏はアフリカの域内である。なぜ熱帯アフリカの森林産物は、世界商品にならなかったのか。ひるがえって、なぜ東南アジア島嶼部のそれはシンガポールやロンドン市場と直結し、世界大の商品となったのか。このような複眼的な問いを立て解をえるためには、アフリカとアジアを歩きまわるしかないようだ。
現在、西アフリカでもプランテーション型のアブラヤシ植栽が進んでいる。いままで触れてきた伝統的なアブラヤシに対して、拡大中のものはマレーシアやインドネシアで目にする短躯多葉なハイブリッド種である。ギニアで訪れたプランテーションは、まさに私たちがマレーシアで馴染んでいるものである。これらの椰子から生産される油は、ローカル種からできる食用油とは異なる生産システムと流通経路を形成している。ギニアでのアブラヤシ・プランテーション開発は、その緒についたばかりであり、東南アジアのそれと比して規模も小さい。この産業の未来は、マレーシアやインドネシアが経験したように労働の組織化をどう行うかにかかっている。マレーシアのように国外の低賃金労働者を動員できるのか。はたまたインドネシアのように小農を組みこんだ生産システムが生まれる可能性があるのか。注目していきたいところである。
 今回の西アフリカ調査では、何を見、何を聞くにつけ、つねに頭のどこかにはサラワクのアブラヤシ・プランテーションが鏡像としてあった。地域間比較の視点からものを見て、考える楽しさを満喫できた旅でもあったといえるだろう。いま考えているのは、ゴムの故地をアマゾンの流域社会に求めることだ。アフリカ西海岸とアマゾンは実は遠くない。奴隷交易の時代を偲びながら、西アフリカ沿岸から海をこえてブラジルを訪れる旅を思案中である。
今回の西アフリカ調査では、何を見、何を聞くにつけ、つねに頭のどこかにはサラワクのアブラヤシ・プランテーションが鏡像としてあった。地域間比較の視点からものを見て、考える楽しさを満喫できた旅でもあったといえるだろう。いま考えているのは、ゴムの故地をアマゾンの流域社会に求めることだ。アフリカ西海岸とアマゾンは実は遠くない。奴隷交易の時代を偲びながら、西アフリカ沿岸から海をこえてブラジルを訪れる旅を思案中である。
注1
アブラヤシまたはギニアアブラヤシ(Elaeis guineensis)はアフリカ原産で、東南アジアには19世紀に導入され、マレーシアでは1960年代から大規模プランテーションでの栽培が増大した。現在の栽培種は品種改良されたもので、一部はアメリカアブラヤシ(Elaeis oleifera)との交配種である。