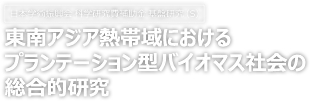先住慣習権とプリミータ・サーベイ(外周測量)
先住慣習権とプリミータ・サーベイ(外周測量)
Logie Seman (元マレーシア・サラワク森林局)
「先住慣習地」(Native Customary Rights Land:NCR Land)とは、先住民が独自の慣習法によって管理運営している土地のことであり、1958年1月1日よりも前に切り拓いた土地が認定の対象となっている。先住慣習地の占有権(利用権)、つまり「先住慣習権」が取得される手続きとしては、1958年に制定された土地法の第5条(2)、第(a)項から(f)項に基づいて登録されるというものである。ただ、これまで、内陸の先住慣習地がきちんと測量・登録されることはほとんどなかった。 サラワク州政府は2011年以降、この「先住慣習地」の外周測量を、土地測量局の主導で実施し始めている。これは現地ではプリミータ・サーベイ(perimeter survey)と呼ばれ、話題になっている。残念なことに、このプリミータ・サーベイに対しては、いくつかのコミュニティが測量に賛同してはいるものの、多くの先住民が反対の意向を示している。 プリミータ・サーベイは、先住慣習地に対して土地権を付与するものであるとされる。1958年1月1日よりも前に拓かれた土地で、サラワクの土地法に沿って法的に認められた先住慣習地は、サラワク全体で150万ヘクタールほどの面積になると推定されているが、これまでそうした先住慣習地が測量されることはなく、開発に直面した時に、先住民と企業の間で土地権を争って、頻繁に衝突が引き起こされてきた。プリミータ・サーベイは、こうした土地を測量し、土地権の証書を発行するというのである。 ただ、サラワクの先住民は、先住慣習地に関して、「利用する権利」を持つということであって、土地そのものを「所有」するわけではない。根本的な問題は、こうした土地に関して、どのような権利を設定するのかということである。また、プリミータ・サーベイそのものについても、その実施の法的・行政的な意図がどこにあるのか疑問が残る。 2012年2月には、プリミータ・サーベイに関する一般向けのフォーラムがクチンで開催され、筆者も参加したが、そのフォーラムにおいても多くの反対意見が出された。その反対意見というのは、「先住慣習地」への権利問題に関連した先住民に対する長期的な影響を懸念したもので、次のような形で要約できる。 a)プリミータ・サーベイを行おうとする地区の現地住民は、土地測量局の担当者に対して、彼らの村落と隣接村落との境界についての根拠を示す必要があるが、それ自体が容易ではない。 b)プリミータ・サーベイの対象には、若い焼畑休閑林や焼畑直後の土地、あるいは現在何かが植えられているという土地ばかりではなく、「プマカイ・ムノア」や「プラオ」なども含まれ、それらの森林への占有権が認められるかという疑念を多くの村人が持っている。 c)「プングラン」と呼ばれるような森や、たとえば80年以上も前に焼畑などの農業活動によって切り開かれた休閑林などはどうなるのか。それくらいの古い休閑林であれば、商品価値の高い大きな木がたくさんあって、今日では原生林のようにも見える場合がある。これらの古い森林に対する先住民の占有権が認められるかどうかについても、村人の不安が残る。 d)かつて耕作されたり占有されたりしていた森林に対して、ブルネイ・スルタンやブルック政府、イギリス直轄植民地政府は、先住民の土地慣習権を認めてきたが、独立後のマレーシア政府による承認は十分ではない。今回のプリミータ・サーベイについて、慣習権がどう設定・承認されるのか、不透明な部分が残っている。 フォーラムに参加していたすべての講演者やパネリストたちが強調していたのは、プリミータ・サーベイは、第5条および第6条に沿うのではなく、土地法の第18条(1)(2)(3)および(4)に基づいて実施されるべきであるということであった 。その主な理由は以下のとおりである。 a)ブルック政府およびイギリス直轄植民地政府によって認知され、設定された「先住慣習地」は、あいまいさを持っており有効なものではないとみなされること。 b)現在の土地法第5条および第6条を適用することで、政府が先住民に対して「先住慣習権」を「与えてやっている」ようにみなしうること。 c)先住慣習権は、第18条が適用されない限り消失しうること。 d)「先住慣習地」に関する現在の法律では、ロングハウスや集落のある場所を含め、先住民たちの慣習地について、その所有権が認められないのはもちろんのこと、そうした場所を彼らが不法占拠しているというようにもみなされうること。つまり、現行法では、「先住慣習地」に関して土地所有権を保証するものは何もないということを意味している。 ブルックがサラワク統治を開始した1841年以前までさかのぼれば、ブルネイのスルタンは先住民の土地(native land)の存在を認知していた。また、ブルック政府も先住民の土地占有権(land tenure)と、アダット(慣習法)による土地の管理を認めていた。イギリス直轄植民地政府は、このような先住慣習地が、サラワクの独立およびマレーシア連邦加盟(1963年9月16日)後も、引き続き存在するものとみなしていた。しかし、この部分について、どのように認識・解釈するかで、先住民側の見方と政府見解との間で対立が生じてきたのである。 先住慣習地であることの証明は、先住民自身がしなければならないことになっているが、それは往々にして困難を伴う。また、開拓や耕作とは別に狩猟や漁撈といったものが土地利用の権利として含まれるかどうかは、解釈に差が生じてくることもある。このように、土地という目に見える存在に対して、眼に見えない利用権というものを証明するのは、非常に難しい。 これまで、「先住慣習地」の権利をめぐって高等裁判所で争われた裁判の約90%で、先住民の権利が正当なものとして認められている。サラワク州政府は現在までのところ、こうした司法の判断を「静観」している。しかし、すべての場合とは言わずとも、ほとんどの場合、アブラヤシ・プランテーションなどの開発企業は、控訴裁判所に上告してきた。そして企業は、裁判の引き延ばしを行うことで、その間にも通常のルーチンの開発活動を進めることができるのである 。 司法の優位性というものが、ブルックや植民地政府による土地認識、先住民支援を行う弁護士、慣習法である「アダット」などにとっては、肯定的な影響力を持ってきたが、土地法の「先住慣習地」に関わる部分については、これまで十分な改善がなされているわけではない。現在でも、審議にかけられて判断されるべき100件以上の事案が残されており、土地権に関して曖昧な部分が残っていることは事実である。 先住民は、プリミータ・サーベイが、第18条を適用する形で実施されることを望んでいる。そうすれば、個人の土地の所有権が永続的に確保できると考えているからである。しかし州政府は、ロングハウスや村落における個人の土地が測量され、いずれは第18条の下で、土地所有権が付与されるであろうことを約束しつつも、プリミータ・サーベイはまず第5条および第6条に沿う形で行われることを強調している。 プリミータ・サーベイの第1段階は、サラワク土地法第5条および第6条に準拠した形で実施される(村落の共有地として測量される)。そして、第2段階として、個人の占有地が測量され、土地法第18条に準拠して土地権が発行されるとしている。ただ、これらの測量作業には12~15年を要すると見込まれており、その費用は4億リンギットにも上ると言われる。実現可能性に疑問が残る。 ジュラロン川流域においては、支流のクブル川沿いのルマ・ジュソンがプリミータ・サーベイを受け入れた事例として挙げられる。ルマ・ジュソンの領域には、休閑林temudaや、プマカイ・ムノアpemakai menoa、プラオ・ガラオpulau galauなどが含まれている。この場所において、土地法第5条および第6条に沿った形でプリミータ・サーベイが行われたのである。 ただ、土地法第5条(3)では、「いかなる慣習権も、大臣の発する指示によって消滅されうる・・・」と述べられている。また、土地法第6条(1)および第7条(1)も、先住慣習地を州有地に転換できる内容ととらえられるもので、これも問題含みの条項となっている。このように、プリミータ・サーベイを行ったとしても、土地法第5条および第6条に基づいたものである限り、土地占有権に対する保証はないということになるのである。 [解説] プリミータ・サーベイというのは、2010年にコンセプトが発表され、2011年から実質的に始まったとされているが、その本来的な意図については、現時点ではまだ分かっているわけではない。政府の言説としては、村の領域確定を行うための安価で有効な手段であるという。村の中で合意が取れた場合、土地測量局に連絡すれば、無料で測量・土地登記を行ってくれるという。 これまで内陸のほとんどの土地は測量も登記もされていなかったため、土地問題が起こった場合には、どこまでが地元先住民の土地なのか、どこが境界になるのか、それらの根拠はどこにあるのか、という点がしばしば問題として顕在化していた。しかし、プリミータ・サーベイによって村の領域(イバン語で言えば、プマカイ・ムノア:pemakai menoa)が測量され、それが土地法に基づいて登記されれば、村外からのさまざまな干渉(たとえばプランテーション開発など)にも法的根拠に基づいて対処できるようになるというのである。これが事実であれば、先住民にとっても自分たちの土地を守る有効な手段になりうる。 ただ、このプリミータ・サーベイには様々な問題がある。ここでは、ロギー氏の文章に関わる重要な2点のみ指摘しておきたい。 1つは1958年ルールの存在である。現行の土地法では、1958年よりも前に森林を拓いたことがあれば、そこは先住民の慣習に基づいて、森林を拓いた者に占有権(利用権)を認めるとしている。しかし、村の領域内には、焼畑に使ったことのない原生林もあれば、1958年以降に拓いた土地もある。これらの土地は村の領域内に含まれるのかどうか、その点が明確になっていない。これまでは、そうした土地は、暗黙の了解のうえで先住民によって利用されたり保護されたりしてきた場合もあれば、伐採企業やプランテーション企業によって開発され、先住民との間で衝突を引き起こす例も見られた。これらが、1958年土地法によって厳密に線引きされると、そもそも先住慣習権のない場所として、政府に取り上げられてしまうのではないかという疑念が、先住民社会の中に残っている。 2つ目の問題点は、プリミータ・サーベイが土地法の第5条および第6条に基づいて行われるという点である。ごく簡単に言えば、第5条および第6条は村落の境界に関わる条項であり、第18条は個人の土地に関わる条項である。要するに、多くの先住民は、村落単位の境界設定ではなく、個人の土地の登記をしたいと考えているのである。多くの先住民は、村落の境界というものが曖昧さを残すものであり、これまでのさまざまな土地問題を振り返ってみても、解釈の仕方によっては、政府や企業に土地を接収される可能性があるという疑念をぬぐいきれない。しかし、個人の土地が登記されれば、その土地の権利はかなり強いものとして確保できると考えている。 これらのことをジュラロン川流域に当てはめて考えてみると、次のことがいえる。第1に、概してプナン集落ではプリミータ・サーベイを受容する傾向が強く、イバン集落において反対意見や疑念が強い。これは民族的な相違が関係している可能性があるが、それ以上に、イバンにとっては上述の1958年の土地法が影響している。ジュラロン川流域のイバンは、1950年代末から1960年代にかけて移住してきた。その当時、ビントゥルの行政官の仲介で、プナンからイバンが土地を分け与えてもらったという形になっており、それらの文書も残されている。それらの文書には「村の領域(プマカイ・ムノア)」が明示されており、イバンがこの地に居住できる根拠になっているが、彼らが1950年代末以降にこの地にやってきたことが明確である以上、これらの土地には、1958年土地法で規定している先住慣習権が発生しないことになる。 彼らが恐れるのは、プリミータ・サーベイによる村落領域の確定によって、植民地期の行政官のサインの入った文書が反故にされる可能性である。移住当時の合意文書が破棄され、1958年土地法によっても先住慣習権が保証されないとなった場合、それでは、プリミータ・サーベイというものが、本当に自分たちの居住や土地利用の新たな根拠になりうるのか、現時点では明確になっていない。こうした土地についての権利関係が依然として不明瞭であるために、ジュラロン川流域のイバンにとっては、プリミータ・サーベイに簡単に同意することができないのであろう。 (日本語訳・解説:祖田 亮次)
「先住慣習地」(Native Customary Rights Land:NCR Land)とは、先住民が独自の慣習法によって管理運営している土地のことであり、1958年1月1日よりも前に切り拓いた土地が認定の対象となっている。先住慣習地の占有権(利用権)、つまり「先住慣習権」が取得される手続きとしては、1958年に制定された土地法の第5条(2)、第(a)項から(f)項に基づいて登録されるというものである。ただ、これまで、内陸の先住慣習地がきちんと測量・登録されることはほとんどなかった。 サラワク州政府は2011年以降、この「先住慣習地」の外周測量を、土地測量局の主導で実施し始めている。これは現地ではプリミータ・サーベイ(perimeter survey)と呼ばれ、話題になっている。残念なことに、このプリミータ・サーベイに対しては、いくつかのコミュニティが測量に賛同してはいるものの、多くの先住民が反対の意向を示している。 プリミータ・サーベイは、先住慣習地に対して土地権を付与するものであるとされる。1958年1月1日よりも前に拓かれた土地で、サラワクの土地法に沿って法的に認められた先住慣習地は、サラワク全体で150万ヘクタールほどの面積になると推定されているが、これまでそうした先住慣習地が測量されることはなく、開発に直面した時に、先住民と企業の間で土地権を争って、頻繁に衝突が引き起こされてきた。プリミータ・サーベイは、こうした土地を測量し、土地権の証書を発行するというのである。 ただ、サラワクの先住民は、先住慣習地に関して、「利用する権利」を持つということであって、土地そのものを「所有」するわけではない。根本的な問題は、こうした土地に関して、どのような権利を設定するのかということである。また、プリミータ・サーベイそのものについても、その実施の法的・行政的な意図がどこにあるのか疑問が残る。 2012年2月には、プリミータ・サーベイに関する一般向けのフォーラムがクチンで開催され、筆者も参加したが、そのフォーラムにおいても多くの反対意見が出された。その反対意見というのは、「先住慣習地」への権利問題に関連した先住民に対する長期的な影響を懸念したもので、次のような形で要約できる。 a)プリミータ・サーベイを行おうとする地区の現地住民は、土地測量局の担当者に対して、彼らの村落と隣接村落との境界についての根拠を示す必要があるが、それ自体が容易ではない。 b)プリミータ・サーベイの対象には、若い焼畑休閑林や焼畑直後の土地、あるいは現在何かが植えられているという土地ばかりではなく、「プマカイ・ムノア」や「プラオ」なども含まれ、それらの森林への占有権が認められるかという疑念を多くの村人が持っている。 c)「プングラン」と呼ばれるような森や、たとえば80年以上も前に焼畑などの農業活動によって切り開かれた休閑林などはどうなるのか。それくらいの古い休閑林であれば、商品価値の高い大きな木がたくさんあって、今日では原生林のようにも見える場合がある。これらの古い森林に対する先住民の占有権が認められるかどうかについても、村人の不安が残る。 d)かつて耕作されたり占有されたりしていた森林に対して、ブルネイ・スルタンやブルック政府、イギリス直轄植民地政府は、先住民の土地慣習権を認めてきたが、独立後のマレーシア政府による承認は十分ではない。今回のプリミータ・サーベイについて、慣習権がどう設定・承認されるのか、不透明な部分が残っている。 フォーラムに参加していたすべての講演者やパネリストたちが強調していたのは、プリミータ・サーベイは、第5条および第6条に沿うのではなく、土地法の第18条(1)(2)(3)および(4)に基づいて実施されるべきであるということであった 。その主な理由は以下のとおりである。 a)ブルック政府およびイギリス直轄植民地政府によって認知され、設定された「先住慣習地」は、あいまいさを持っており有効なものではないとみなされること。 b)現在の土地法第5条および第6条を適用することで、政府が先住民に対して「先住慣習権」を「与えてやっている」ようにみなしうること。 c)先住慣習権は、第18条が適用されない限り消失しうること。 d)「先住慣習地」に関する現在の法律では、ロングハウスや集落のある場所を含め、先住民たちの慣習地について、その所有権が認められないのはもちろんのこと、そうした場所を彼らが不法占拠しているというようにもみなされうること。つまり、現行法では、「先住慣習地」に関して土地所有権を保証するものは何もないということを意味している。 ブルックがサラワク統治を開始した1841年以前までさかのぼれば、ブルネイのスルタンは先住民の土地(native land)の存在を認知していた。また、ブルック政府も先住民の土地占有権(land tenure)と、アダット(慣習法)による土地の管理を認めていた。イギリス直轄植民地政府は、このような先住慣習地が、サラワクの独立およびマレーシア連邦加盟(1963年9月16日)後も、引き続き存在するものとみなしていた。しかし、この部分について、どのように認識・解釈するかで、先住民側の見方と政府見解との間で対立が生じてきたのである。 先住慣習地であることの証明は、先住民自身がしなければならないことになっているが、それは往々にして困難を伴う。また、開拓や耕作とは別に狩猟や漁撈といったものが土地利用の権利として含まれるかどうかは、解釈に差が生じてくることもある。このように、土地という目に見える存在に対して、眼に見えない利用権というものを証明するのは、非常に難しい。 これまで、「先住慣習地」の権利をめぐって高等裁判所で争われた裁判の約90%で、先住民の権利が正当なものとして認められている。サラワク州政府は現在までのところ、こうした司法の判断を「静観」している。しかし、すべての場合とは言わずとも、ほとんどの場合、アブラヤシ・プランテーションなどの開発企業は、控訴裁判所に上告してきた。そして企業は、裁判の引き延ばしを行うことで、その間にも通常のルーチンの開発活動を進めることができるのである 。 司法の優位性というものが、ブルックや植民地政府による土地認識、先住民支援を行う弁護士、慣習法である「アダット」などにとっては、肯定的な影響力を持ってきたが、土地法の「先住慣習地」に関わる部分については、これまで十分な改善がなされているわけではない。現在でも、審議にかけられて判断されるべき100件以上の事案が残されており、土地権に関して曖昧な部分が残っていることは事実である。 先住民は、プリミータ・サーベイが、第18条を適用する形で実施されることを望んでいる。そうすれば、個人の土地の所有権が永続的に確保できると考えているからである。しかし州政府は、ロングハウスや村落における個人の土地が測量され、いずれは第18条の下で、土地所有権が付与されるであろうことを約束しつつも、プリミータ・サーベイはまず第5条および第6条に沿う形で行われることを強調している。 プリミータ・サーベイの第1段階は、サラワク土地法第5条および第6条に準拠した形で実施される(村落の共有地として測量される)。そして、第2段階として、個人の占有地が測量され、土地法第18条に準拠して土地権が発行されるとしている。ただ、これらの測量作業には12~15年を要すると見込まれており、その費用は4億リンギットにも上ると言われる。実現可能性に疑問が残る。 ジュラロン川流域においては、支流のクブル川沿いのルマ・ジュソンがプリミータ・サーベイを受け入れた事例として挙げられる。ルマ・ジュソンの領域には、休閑林temudaや、プマカイ・ムノアpemakai menoa、プラオ・ガラオpulau galauなどが含まれている。この場所において、土地法第5条および第6条に沿った形でプリミータ・サーベイが行われたのである。 ただ、土地法第5条(3)では、「いかなる慣習権も、大臣の発する指示によって消滅されうる・・・」と述べられている。また、土地法第6条(1)および第7条(1)も、先住慣習地を州有地に転換できる内容ととらえられるもので、これも問題含みの条項となっている。このように、プリミータ・サーベイを行ったとしても、土地法第5条および第6条に基づいたものである限り、土地占有権に対する保証はないということになるのである。 [解説] プリミータ・サーベイというのは、2010年にコンセプトが発表され、2011年から実質的に始まったとされているが、その本来的な意図については、現時点ではまだ分かっているわけではない。政府の言説としては、村の領域確定を行うための安価で有効な手段であるという。村の中で合意が取れた場合、土地測量局に連絡すれば、無料で測量・土地登記を行ってくれるという。 これまで内陸のほとんどの土地は測量も登記もされていなかったため、土地問題が起こった場合には、どこまでが地元先住民の土地なのか、どこが境界になるのか、それらの根拠はどこにあるのか、という点がしばしば問題として顕在化していた。しかし、プリミータ・サーベイによって村の領域(イバン語で言えば、プマカイ・ムノア:pemakai menoa)が測量され、それが土地法に基づいて登記されれば、村外からのさまざまな干渉(たとえばプランテーション開発など)にも法的根拠に基づいて対処できるようになるというのである。これが事実であれば、先住民にとっても自分たちの土地を守る有効な手段になりうる。 ただ、このプリミータ・サーベイには様々な問題がある。ここでは、ロギー氏の文章に関わる重要な2点のみ指摘しておきたい。 1つは1958年ルールの存在である。現行の土地法では、1958年よりも前に森林を拓いたことがあれば、そこは先住民の慣習に基づいて、森林を拓いた者に占有権(利用権)を認めるとしている。しかし、村の領域内には、焼畑に使ったことのない原生林もあれば、1958年以降に拓いた土地もある。これらの土地は村の領域内に含まれるのかどうか、その点が明確になっていない。これまでは、そうした土地は、暗黙の了解のうえで先住民によって利用されたり保護されたりしてきた場合もあれば、伐採企業やプランテーション企業によって開発され、先住民との間で衝突を引き起こす例も見られた。これらが、1958年土地法によって厳密に線引きされると、そもそも先住慣習権のない場所として、政府に取り上げられてしまうのではないかという疑念が、先住民社会の中に残っている。 2つ目の問題点は、プリミータ・サーベイが土地法の第5条および第6条に基づいて行われるという点である。ごく簡単に言えば、第5条および第6条は村落の境界に関わる条項であり、第18条は個人の土地に関わる条項である。要するに、多くの先住民は、村落単位の境界設定ではなく、個人の土地の登記をしたいと考えているのである。多くの先住民は、村落の境界というものが曖昧さを残すものであり、これまでのさまざまな土地問題を振り返ってみても、解釈の仕方によっては、政府や企業に土地を接収される可能性があるという疑念をぬぐいきれない。しかし、個人の土地が登記されれば、その土地の権利はかなり強いものとして確保できると考えている。 これらのことをジュラロン川流域に当てはめて考えてみると、次のことがいえる。第1に、概してプナン集落ではプリミータ・サーベイを受容する傾向が強く、イバン集落において反対意見や疑念が強い。これは民族的な相違が関係している可能性があるが、それ以上に、イバンにとっては上述の1958年の土地法が影響している。ジュラロン川流域のイバンは、1950年代末から1960年代にかけて移住してきた。その当時、ビントゥルの行政官の仲介で、プナンからイバンが土地を分け与えてもらったという形になっており、それらの文書も残されている。それらの文書には「村の領域(プマカイ・ムノア)」が明示されており、イバンがこの地に居住できる根拠になっているが、彼らが1950年代末以降にこの地にやってきたことが明確である以上、これらの土地には、1958年土地法で規定している先住慣習権が発生しないことになる。 彼らが恐れるのは、プリミータ・サーベイによる村落領域の確定によって、植民地期の行政官のサインの入った文書が反故にされる可能性である。移住当時の合意文書が破棄され、1958年土地法によっても先住慣習権が保証されないとなった場合、それでは、プリミータ・サーベイというものが、本当に自分たちの居住や土地利用の新たな根拠になりうるのか、現時点では明確になっていない。こうした土地についての権利関係が依然として不明瞭であるために、ジュラロン川流域のイバンにとっては、プリミータ・サーベイに簡単に同意することができないのであろう。 (日本語訳・解説:祖田 亮次)