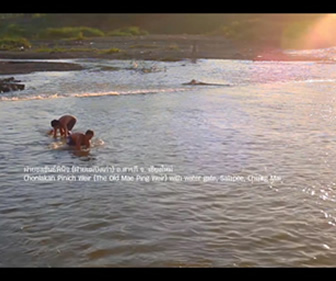京都上映会: 2016年3月23日(水) 京都大学国際科学イノベーション棟
東京上映会: 2016年3月25日(金) 国際交流基金JFICホール [さくら]
プロジェクトについて
東南アジアは、多様な民族、宗教、文化で構成されています。その多様性を共 存させつつ、地域全体としては経済的な前進を遂げ、人、モノ、カネ、情報の流れ のハブとなっています。しかし、同時に、熱帯林の減少や生物多様性の危機、災害、 疫病、高齢化、民族や宗教の抗争、経済的階層化と貧困など、多くの問題も抱えて います。
このような多様性の中で、人々はどのように共存し、社会の持続性はどのように 維持されているのでしょうか。人々の日々の生活を支える地域の社会基盤を、どの ように利用できるでしょうか? そして、それらを既存のガバナンス・システムと組 み合わせて諸問題の解決につなげるには、どうすればよいのでしょうか。
Visual Documentary Project は、これらの疑問への答えを東南アジアの現状に即 して見いだすために、2012年度、京都大学東南アジア研究所が開始した東南アジアの映像作家が制作する短編ドキュメンタリーを募集・上映するプロジェクトです。2014年度から、国際交流基金アジアセンターも共催者として加わり、作品を通して東南アジア地域の現状を捉え、諸問題の解決へとつなげる試みを行っています。
http://www-archive.cseas.kyoto-u.ac.jp/sea-sh/documentary_project_top/
主催:京都大学東南アジア研究所、国際交流基金アジアセンター
協力:Yangon Film School, Documentary Arts Asia, WATHANN FILM FESTIVAL, In-Docs, Bophana Audiovisual Resource Center
Documentaries line-up 2015
越境する東南アジア - Human Flows -
監督紹介

Kunnawut Boonreak
1990年生まれ タイ出身
タイのブラパー大学でジャーナリズムを学び、現在チェンマイ大学の社会学・社会開発学の修士課程在学中。最初のドキュメンタリー作品『Laemchabang, the Wave of Sorrow』が第16回タイ短編映画・ビデオフェスティバルに入選。また今回の作品『Michael’s』は2015年に第19回タイ短編映画・ビデオフェスティバルにてデューク賞2位、またフィリピンの第2回アジトプロップ国際映画祭にて公式招待された。

Hien Anh Nguyen
1995年生まれ ベトナム出身
2013年に高校を卒業後、現在ハノイの法律大学で犯罪学を専攻中。『Dedicated to Granpa DIeu』は、2015年ハノイの短編映画祭にて2つの賞を受賞した。
2人のマイケル / Michael's
監督:Kunnawut Boonreak
タイ北部にあるミャンマーとの国境の町メーソットとウンピアム難民キャンプを舞台に、2人のマイケルに焦点を当てる。同じロヒンギャ※でありながらも、経済的な状況も育ってきた環境も異なる2人は、それぞれ生活に苦労しながらも、タイとミャンマーどちらにも属さないロヒンギャとしての自らのアイデンティティを保とうと奮闘する。
(※ミャンマーのヤカイン州に住む人々の名称)
撮影地:タイ
line-up 2015ジウおじいちゃんへ捧ぐ / Dedicated to Grandpa Dieu
監督:Hien Anh Nguyen
ハノイ市内の騒がしい路地の小さな一角、質素な家で素朴な生活を営む祖父デューの日常生活を描く。ジウは1960年代半ばに国連難民高等弁務官事務所でフリーランスの通訳者として働いていた野心家であり、懸命に好きな本を翻訳してきたが、その本を出版しようと試みたことは一度もなかった。
撮影地:ベトナム
line-up 2015儚さ / Fragile
監督:Bebbra Mailin
マレーシアのサバ州に住むインドネシア人家族の生活を、厳しい生活の中でも、歌手になるという夢を持ち続ける12歳の少女ニルワナの視点から描く。
撮影地:マレーシア
line-up 2015私の足 / My Leg
監督:Khon Soe Moe Aung
ミャンマーのカヤー州では、60年以上に渡り異なる民族の武装勢力が独立を求めてミャンマー軍と戦ってきた。敵味方の区別なく、年間約100足の義足を退役軍人たちに提供している退役軍人による義足の作業場に焦点を当てる。
撮影地:ミャンマー
line-up 2015我が政治人生 / A Political Life
監督:Soe Akhar Htun
ユー・ティン・ソーは、若かりし頃にアウンサンスーチーのボディガードとして自らの青春を捧げ、政治活動に勤しんできた。長い間苦労をかけた妻と家族のために、活動から身を引くことを決断するが、それでも地元の人からの相談事は断れずに、法律相談にのってしまうのであった。
- 撮影地:ミャンマー
line-up 2015Documentaries line-up 2014 -People and Nature in Southeast Asia-
Documentaries line-up 2013 -Plural Co-existence in Southeast Asia-
Documentaries line-up 2012 -“Care”in Southeast Asia: Every Day and into the Future-
上映作品選考委員
リティ・パン監督
講演会『ドキュメンタリーがもつ社会的意義』・インタビュー
Part1 講演会 Part2 質疑応答
リティ・パン監督の来日を記念して、京都大学東南アジア研究所にて作品上映・講演会を行いました。
日時:2015年6月9日(火)
場所:京都大学東南アジア研究所 稲盛財団記念館3階大会議室
上映:『S21クメール・ルージュの虐殺者たち』
講演:『ドキュメンタリーが持つ社会的意義―虐殺の記憶を映画はどう描き、どのように伝えるのか』
質疑応答 モデレーター 小林知(東南アジア研究所)
リティ・パン監督 講演会・インタビュー 〈Part1 講演会〉
 皆さんこんにちは。まず京都大学東南アジア研究所および国際交流基金アジアセンターに感謝をしたいと思います。私にとって皆さんとこのような場でお会いできるのはじつに特権的な瞬間です。ですから皆さんがご来場くださったことに心から御礼申し上げます。
皆さんこんにちは。まず京都大学東南アジア研究所および国際交流基金アジアセンターに感謝をしたいと思います。私にとって皆さんとこのような場でお会いできるのはじつに特権的な瞬間です。ですから皆さんがご来場くださったことに心から御礼申し上げます。
私は映画作家ですから、普段は映画を作ることを仕事にしており、人前で話すことが仕事ではありません。けれども今日、提案された主題について、私なりの見解を述べたいと思います。とても重要なテーマをいただきました。それは大虐殺、大量虐殺の犯罪、記憶におけるドキュメンタリーの力、ドキュメンタリーの役割というテーマです。
まず、大量虐殺の犯罪については、カンボジアの虐殺の場合、180万人のひとが虐殺されたと言われています。その数は当時の人口の4分の1に当たります。果たして殺された180万人というこの数には、一体どういう意味があるのでしょうか。そこがおそらく、大量虐殺の犯罪すなわち人道に反する罪と、町の片隅で起こる通常の犯罪との違いでしょう。
私にとって180万という数は、180万個の人生、180万個の個々の歴史、180万人の顔、180万個の名前です。こうやって虐殺の事実を語るとき、数字はよく出てきますけれども、その筋の後ろに隠れている個人個人の運命がどのようなものなのかが話題になる事はあまりありません。
私たちはすべてのことを知っているような気がしていますが。実際には何も知らないのです。そこで物事が複雑になってきます。実際にこのような虐殺の後、どのようにして国を再建するのか、社会組織を作り上げ、その国の歴史を、その国の集団的な記憶をどのように作り上げるのかという問題が提起されるのです。
そうした死者たちの問題を越えて、その虐殺を実行しようと言う意志があったと言う事、殺戮の意志があったと言う点に、私は興味を持ちます。そのような虐殺を行う意図がなければ、虐殺は行われないはずです。意図がなかったとすれば、それは集団的狂気だったのか何なのかわからないことになります。虐殺を考える時、虐殺をしようという意図があったことを証明しなければなりません。
虐殺は他者を抹殺しよう、消失させてしまおうという試みであり、それは肉体的な身体の抹消をこえてそのアイデンティティすら消し去ろうと言う試みです。
クメール・ルージュの言語においては殺す、処刑するという言葉の代わりに、特別の言葉カムテッチという言葉を使っていました。カムテッチという言葉は、破壊をする、灰燼に帰してしまう、粉々にしてしまうことを意味し、単に殺すという言葉よりさらに多くを物語る言葉です。
記憶のための仕事をすることは、消えてしまった人々に対して、再びアイデンティティを与えることでもあります。名前と顔を与えることです。そして歴史を語るのです。それは個々の歴史であり、我々の歴史であり、我々という集団の歴史であり、私の歴史であり、またあなたの歴史でもあります。だからこそカンボジアで、最初にしなければならない重要な事はドキュメンテーションの仕事でした。そしてその仕事は、クメール・ルージュの歴史を超えて、さらに先へと進んでいかなければなりません。
クメール・ルージュ以前の私たちの歴史を、再び取り戻さなければなりません。その過去の歴史を私たちの現在の歴史に結びつけるのです。虐殺と言うぽかりと空いた大きな穴の上に橋をかけるような仕事です。それが虐殺に関わる仕事です。もし私が成功したとすれば、それは20年かけて二つか三つの顔に名前を与えることができたことです。20年で2人か3人ですからあまり多くはありません。
長く難しい仕事ですがこれは私の歴史ですから、私はその歴史に直面する必要がありました。何も言わないことに満足することもできたでしょう。もう何も発言はしたくないと言う人の意向は尊重します。私自身、話すことによって果たして気分が良くなるかどうか、確信はないからです。
しかし私にとっては、話すことよりも、話さないこと、発言をしないことの方が苦しいことなのです。なぜならば、我々のように虐殺の悲劇を生き延びたものがいても、生き延びることができたのは他の人よりも強いから、他の人よりも勇気があるから、ではないのです。
生き延びることができたのは、他の人たちが助けてくれたからでもあります。そこで、同じ点に立ち返ることになります。虐殺に関するドキュメンタリーの仕事は、他者が誰だったのか、消えてしまったその他者が誰だったのか問いかけることでもあるのです。このようにして私は、どのようにしてもそこから抜け出すことができない、うまくやっていくことができないのです。この歴史から私は逃げることができません。ですから自分に勇気をもたせ、自分を助けてくれた人々、そのおかげで生き延びることできた人々、その人たちに、再び名前を与えなければならないのです。
しかし私はその仕事を多大な希望を持って行っています。その希望とは、ある日、いつかどこかで、こうしたこと全てがうまく終わるだろうという希望です。
その希望は、同じ歴史が繰り返さないだろうという希望でもあります。もちろん私は、歴史は実際には何度も繰り返してしまうということを知ってはいますが。
それは善と悪との戦いのようなものです。悪の方が必ず善よりも強いのです。悪と戦う仕事、記憶の仕事を行うものはいつも弱いものの側にあります。その戦いの中で我々は常にloser(敗者)です。しかしその戦いをしなければならない。その戦いこそが人間に尊厳を与える戦いなのです。尊厳なしに人間は生きることができません。
今ご覧になった映画『S21、クメール・ルージュの虐殺者たち』が撮影されたS21は、クメール・ルージュの刑務所であり、また処刑の場でありました。プノンペンの中心部にあります。
国中に様々なそうした処刑の場があるのに、なぜS21を選んだのかとよく聞かれます。実際にはじめて私がS21に行った時には、どうしてもその中に入ることができませんでした。門の前まで行きながらも、その門をくぐって中に一歩を踏み出すことができませんでした。
けれども、中に入りたいという気持ちは強く持っていました。S21で処刑をされたおじの痕跡を中に入って見つけたいと思っていました。しかし、中に入って処刑場の内部を見ることが何か猥雑な行為であるような気がしたのです。しかし、少しずつ、クメール・ルージュの権力の中心にあったこの殺戮の機械について、考えることが重要であると思うようになってきました。
S21を理解することは、クメール・ルージュの政権を理解することでもあります。S21を理解することは、重要です。ただ、そこで殺された人の数字だけを見ると、S21で殺された人は13,000人弱でありますから、様々な処刑場の中で、S21は処刑者数の数では12位ないし13位にすぎません。けれどもS21は私には特別なものでした。S21は私にとっては国家の中の国家のように見えました。そして何人かの研究者が、実はS21はクメール・ルージュがクメール・ルージュを殺していた、粛清の場であったと教えてくれました。実際には事態はそれ以上に複雑でした。
S21で処刑されたクメール・ルージュの幹部も多くいます。けれども知識人や子供、女性も多くそこで殺されています。また、S21以外の所で、S21で行われたことが原因となって殺されてしまった人がいます。なぜならS21は、逮捕しそして処刑すべき、消滅させるべき人々のリストを作っていたところだったからです。そして殺戮がどのように機械的になされたのかという事をはっきりと見ることが重要でした。そうした恐怖の雰囲気をどのようにしてS21で生み出すことができたのでしょうか?
S21の中で使われていた言葉の語彙はどのようなものだったでしょうか。本当に、様々な問題が広がっており、そこでは考古学者のような取り組みが必要でした。考古学者が寺院の遺跡の研究をするように、私はS21の様々に重なる層を、一つ一つ解き明かして行こうとしました。層から層へ、一点からまた別の一点へと調査をし、掘り下げ、また調査をし、掘り下げていくことを繰り返しました。
S21について、多くの歴史研究がなされています。政治的な研究もされていますが、人類学的研究はされていません。私にとって物事はもっと複雑でした。おわかりかと思いますが、私は映画作家ですから、S21のように犯罪が起こされた場所にカメラを持ち込むと、まさにその瞬間から道徳的・倫理的な問題をはっきりと意識します。映像はすぐに猥雑なものになったり、覗き見趣味になったりする可能性があるからです。映画的に見ても興味深い仕事でした。どのようにすればカメラが記憶を再構築するための道具になり得るか、ということを考える手段でもあったのです。
映画はもちろん主観的なものです。そして私はその主観性を自分のものとして引き受けています。記憶もまた同じです。記憶は何か固定されたものではなく、記憶は変わり、変化し、変貌していきます。ですから、ドキュメンタリーの仕事、映像の仕事が、S21と言う場所で、それなりの場所、自分の場所を見つけなければなりませんでした。
また私にとって、身体の記憶が重要だということにも気づきました。身体の記憶は、言葉や視覚的な記憶以上に重要なものであり、その記憶は明白なものとしてそこにあり、私はそれを撮影することができる、映像にすることができると考えました。
おそらく映画をご覧になって、皆さん驚かれたシーンが1つあるのではないかと思います。それは看守だった人が、当時行っていた動作を再現するところです。様々な人々から、どのようにしてあの人はああいう演技ができたのかとよく尋ねられます。彼は演技をしていたのではありません。彼は俳優ではないのです。
彼は、覚えている何かを、反復し再現したのではありません。私が演出をしたわけでもありません。実際にその動作が出来る人は二人だけしかいません。その一人は囚人で、その囚人は殺されていますから、その動作を再びすることはできません。もう一人その動作が出来る人は虐殺者です。私自身はその動作が時間的にどのような順番なのかということは知り得ることはできません。
実は、この動作には決まった順序があり、どのような順序でもいいとうものではないのです。そのような身体の記憶、体の記憶を捉えるという点で、映画の仕事は興味深いものになりました。
ユダヤ人の虐殺の場合でも、カンボジアの虐殺の場合でも、多くの生存者がいます。生き延びた人々は、傷を受けており、たとえその傷が癒えたとしても、30年後もなおその傷の痛みを感じて続けています。虐殺者にしても同じです。その暴力性のある動作が、いわば彼自身の中にある暴力性が無意識的な記憶として蘇ってきて、その瞬間をカメラが捉えることができるのです。それが、S21の働きに関してこの映画で自分が展開しようとした重要な点の一つでした。
もう一つ、厳密に言うために述べておかなければいけないことは、犠牲者と虐殺者たちをこのように対決させようと、私が思いついたわけではないということです。それは、S21の撮影の2、3年前に、偶然の出会いがあり、そこからなされたことです。
もう一本別の作品、『ボパナ、カンボジアの悲劇』という作品を撮っていたときのことでした。その撮影では、虐殺者の側にいた人の一人にインタビューをしたいと考えました。
S21に出てくる画家、ヴァン・ナットは、生存者であり、彼が虐殺者と会うことを私は望んでいませんでした。そこで別々に撮影をしました。私は、犠牲者と虐殺者の側にいた人とを会わせる、むりやり出会わせるような権利は私にはないと思っていたのです。そして、虐殺者の側の人々は、いつもS21の外で、別のところで撮影をしました。そして画家のヴァン・ナットのインタビューは、S21の中で行いました。
ある日、虐殺者を撮影しているときに、雨が降り始めました。そこでS21の建物の中で撮影をすることにしました。雨が降っているからS21の建物の中でもいいだろうと思ったのです。そこで、私の助監督の一人に、その日は中で撮影をしているから、ヴァン・ナットに来ないように言ってくれとたのみ、伝言を言いに行かせました。
翌日、S21の看守の看守長であったホイと仕事を始めました。朝の10時、11時ぐらいだったでしょうか、ヴァン・ナットがS21にやってくるのが分かりました。私はヴァン・ナットとホイの間で何か起きるのではないか心配になりましたが、ヴァン・ナットのほうはとても落ち着いており、ホイの様子を30分ほど観察していたでしょうか。そのあとヴァン・ナットはホイに近づき、彼に話しかけました。驚いたことに、ヴァン・ナットはホイの肩のところに手を置いて、彼を案内し、自分が描いていたS21の絵を彼に見せたのです。ヴァン・ナットはS21でどのような犯罪が行われていたかを絵画で描いていました。彼は、元看守にそれを見せ、説明をしました。
ヴァン・ナットはS21の中で行われていた犯罪を絵画で表していたのですが、ヴァン・ナットはホイに対し、絵一枚一枚に関して、果たして本当にこうだっただろうか、これで正しいだろうか、と問いかけました。例えば、このシーンは自分では実際に見てないけれど、話を聞いてこのように描いた、誇張しすぎてないだろうか、というふうにホイに尋ねたのです。そうするとその度に、ホイは確かにこの通りだった、そうだ、まったくこのようなことが起きていた、というように返事をしていました。実際に私の眼の前で、素晴らしい記憶の行為が起きていたのです。
その後、私はプリーモ・レーヴィの「アウシュビッツは終わらない----これは人間か」という本の中で、ある一節を読みました。プリーモ・レーヴィにはナチスの強制収容所からイタリアの自宅に帰る途中、ひとつ非常に恐れていたことがありました。それは、自分がナチの強制収容所の話をしても、誰も信じてくれないのではないか、という恐れでした。
そこで初めて私は、画家ヴァン・ナットのした行為の意味がわかりました。クメール・ルージュの看守長を連れてきて、本当にS21で起きていたことを確認していたのです。
従って、ヴァン・ナットは、S21に関する記憶の仕事を、絵画において見事に行っていたわけです。素晴らしい絵画ですが、絵画でありますから主観的なものです。
ヴァン・ナットは犠牲者の側からの証言をおこないましたが、犠牲者の側の証言だけでは足りません。加害者のほうからの証言も必要です。
お分かりのように映画とはとても奇妙なものです。私の方がこうした犠牲者と加害者との間の対決、出会いを作ろうと決めたのではなく、そのような二人の対決が、重要で必ず必要なものとして、向こうの方から私のところに、やってきたのです。私の側でそれを決めたのであれば、それは残念な結果に終わったでしょう。単なる演出にすぎませんから。
おそらくそうした瞬間が、私がドキュメンタリー映画にこだわり続ける唯一の理由なのかもしれません。そこにはいつも何か人間的なものがあります。このようなテーマを扱う際には、ドキュメンタリーに対して信念をもっていなければなりません。その信念は、ほとんど宗教的な信仰にも近い信念であります。すなわち、人間存在を完全に破壊することはできない、必ず記憶の痕跡が残っており、クメール・ルージュが虐殺によって行おうとしたような、完全に消滅させようとする誘惑に打ち勝つような証言、記憶の痕跡がかならずあるのだという信念です。
以上、みなさんと議論をするために、導入になればと思ってお話しました。どのような質問でも結構ですから、どんどん質問をなさってください。
リティ・パン監督 講演会・インタビュー 〈Part2 質疑応答〉
- 小林:
はい。それでは、貴重な講演をありがとうございました。(質疑応答を)始める前に、私は、たぶん、質問は3種類くらい出てくるだろうと。一つはS21というこの映画について、より知りたいという質問、もうひとつは、S21とその背景をもうすこし広く捉えて、クメール・ルージュの時代のカンボジアというのが生まれた、そういう状況について。で、最後にですね、今日の講演では、ドキュメンタリー・フィルムの社会的意義という大きなタイトルがありましたので、その部分でも質問があるかな、というふうに考えてきました。
で、講演をお聞きして、実際、いま私が設定した三つのことの、S21について、そしてクメール・ルージュ時代のカンボジアについて、そして、ドキュメンタリー・フィルムについてですね、それぞれ、もうすでに講演のなかで、かなり具体的な監督の意見が、お聞かせいただいたと思います。特に虐殺というのは、カムテッチ、要するに「消去する」「存在自体を消してしまう」ことになる、という認識と、それに、消え去った人にもう一回名前をあたえて、顔を与えるということが、そういうことで歴史を語るということが、虐殺を映像化するということの、最大の目的だというお話がありました。
で、S21というこの機関についても、かなり詳しいご説明がありました。
え~、インタビューの場面ですね、特にヴァン・ナットさんという絵描きさんと、看守たちとの出会いというのが、ありました。その出会いが、どういう形で生まれたのかということは、初めて私も知りましたが、非常に興味深いものだと思います。
で、質問がいくつかあります。まず、一つ目の質問はですね、S21の具体的な、場面についての質問がひとつあります。ヴァン・ナットさんが、守衛の方に対して、「君たちは動物のようになった」、という、非難というか、そういうコメントを、残しています。ただし、質問者の方は、動物というのは、お互いに拷問したり、殺しあったりしないだろうと。拷問するのは人間だろうというコメントが寄せられています。まずこの問いについて、監督はどう思われますか、という質問が一つありました、ということをご紹介したい。
- パン監督:
拷問するのが人間なのか、はたして拷問するのがイデオロギーなのか分からないのではないでしょうか。人間の運命について悲観的になってはならないと思います。人間は完全に善であることもなければ完全に悪であることもないのです。ただし、イデオロギーのほうは、より動物的とされる野蛮な本能を刺激することがあります。
今日の話のはじめに、私は「虐殺の意図」ということばを使いました。その意図について、考えなければならないことがあります。大虐殺の場合、それがユダヤ人の虐殺であってもカンボジアの虐殺であっても、かならず、虐殺の前に「非人間化」、人間でないものにしようとするプロセスが存在します。ですから、人間ではないものにするということで、動物という言い方をするのは、適切ではないでしょうか。
たとえば60人、100人を一度に虐殺するにしても、カンボジアの場合は180万人が犠牲になったわけですから、非人間化のプロセスなしに殺すことはできません。ただしその非人間化されるのは犠牲者だけでなく、虐殺者も非人間化されるのです。
また、平和を取り戻そうとするとき、そして、記憶を修復していこうとするとき、その試みをするのは虐殺の犠牲者となったひとだけあってはなりません。かならず双方が記憶の努力をしなければなりません。ひとりだけではその仕事はできません。ただ、犠牲者のみが、その記憶を取り戻すという仕事の重みを背負うのであってはならないのです。
驚くべきことがあります。S21の虐殺者たちに単純な質問をします。「一体何人の人を殺したか?」と訊くと、答えは返ってきません。彼らがわかっていないからではありません。彼らにとって答えをいうことは不可能だからです。
なぜならば、彼らが破壊をしなければならないのは敵であって、その彼らが破壊する敵は、おそらくもう何も人間的なところを持っていなかったのです。外見すら人間的だとは思えなかったのかもしれません。
私のような映画を作る側にとって、それはとても複雑なことでした。S21の1日の仕事を語ってもらっているとき、もはや生命が無意味に見えるようなところがあるのです。S21は極めて奇妙な世界でした。すなわち、何人殺したのかと訊いても、4人殺したとか、10人殺したなどの答えは返ってきません。そうした質問に答えが返ってきませんから、その方向では私の調査を進めることはできません。
一つ例をあげるとすれば、私が質問をするシーンがあります。「よくそこに行ったか?」と訊くと、「よく行った。」というふうに答えが返ってきます。しかし、何人殺したのかは思い出すことができない。なぜならば初めて人を殺したときの思い出は明確ですが、200回、1000回と繰り返されていくと、もはや思い出には残らないのです。そうすると殺された1000人のひとびとは、全くアイデンティティがないのと同じです。
これは説明をするのが難しいのですが、一人だけを殺したのであれば、その人が男だったか女だったか、名前や時間や、その殺した瞬間のことを憶えているでしょう。それが、1000人、10000人になると、もう何も憶えていない、なんでもないことになってしまうのです。30年経ったいま、何人が殺されたとか、そういうふうに単なる数字を挙げることは全く同じです。
すなわち、それぞれの歴史やそれぞれの名前もなく、殺された人数だけを挙げている時、そのひとびとは人間として扱われておらず、非人間化のプロセスが30年経った今も働き、私たちにのしかかっているのです。だからこそドキュメンテーションの仕事はとても重要だとおもいます。あのホイの場合も、何人自分が殺したかは言うことができません。彼自身が「1回目、2回目と殺して、その後もうなにも感じなくなった。」「血の匂いも感じなくなった。」と言っています。
これが、ひとびとを抹殺してしまうという仕事です。ルワンダの虐殺にしても同じでした。殺人をする、殺すということばは使われませんでした。ただ「couper切る」ということばを使っていました。それは木を切る、葉っぱを切る、枝を切るのと同じように、「切る」ということばを使っていたのです。
- 小林:
はい、ありがとうございました。問いかけた以上の、たくさんの印象的な、心に残る言葉をお聞きできたとおもいます。質問は他にも、例えばですね、「看守たちは、後悔の念とか責任の念なんかを感じているように見えなかった、それはなぜか」といった質問もありました。でも、それについての答えは、いま監督がお話しになった中にあるのだろうと思います。
- パン監督:
それは、現在にも通じる重要な問題だと思います。それは、果たして同様なことがいま起きたとき、たとえば原理主義の中にいるひとが、再び人間の社会にもどって人間的になれるかどうかという問題にもつながってくるからです。
犯罪は、残念ながらとても人間的なもの、人間のものだと思います。悲しいことに、罪を犯すことはあまりにも人間的な行為なのではないでしょうか。あまりにも罪が人間的であるから、はたして、自分がそれに対して後悔をしているといえば、より人間的になれるのかどうか、それはとても複雑な問題です。
現在、もうひとつ問題になるのは、どのようなレベルでその犯罪に関与していたのかということでしょう。その疑問に対して、全てに当てはまるような簡単なことでは、いまはないと思うのです。たとえば、S21の所長だったドッチですけども、彼のほうが実際に処刑に携わっていたひとよりも責任があるのか、あるいは技術的に実際に殺していたひとの責任のほうが重いのか、その度合いを測ることも難しいことだと思います。
そうやっていちど非人間化されて虐殺者になったひとびとが、はたして人間の側にもどることにできるのか、文明の側に戻ることができるのかという問題は、現代では過激派組織イスラム国ISについて提起されるのではないかと思うのです。
ISのひとびとは、他から連れきた人たちの首を切っています。はたしてそのひとびとが、社会に戻ることができるかどうか、それは大変重要な問題でしょう。私自身は、彼らが人間社会、文明の側に戻ってくることができるかどうか、疑わしく思います。これは全てのひとびとにとって大変不幸なことですけれども。

S21の場合、そこで犯罪を犯していたひとびとは、16歳から20歳でした。そして30年、35年経った現在、再び虐殺をしようともちかけられると、それができるような人たちもそのうちに何人かはいるでしょう。けれども他のひとびとはもはや同じことはできません。そして全員が、眼差しの中に悲しみをたたえています。言葉で語ることはできません。後悔しているという言葉は絶対に出てきません。
なぜならば非人間化のプロセスがありますから、S21のメカニズム自体に、ひとを殺すことに対する後悔ということばは存在をしなかったのです。もし後悔できるようだったら、殺すこともできなかったでしょう。後悔の念を感じることができないようにしているのです。
また30年経ったいま、殺人は非合法的な行為ですが、当時、かれらの行っていた虐殺は合法的な行為であったことを思い出してください。国家が命令をして虐殺をさせていたのです。かれらは警察の一員、治安部隊の一員でありました。国家が認めた行為、国家から命令された行為をしていただけです。サンテバルという治安部隊の一員でありましたから、国家の治安を守るために、敵を殺していたのです。
そこで、30年40年経った時、かれらが罪の意識を感じることができるかどうか、それは疑わしいものだと思います。犯罪のなかでどこまでが個人の責任なのか、どのように個人の責任を分節化するか、果たしてそれができるのかという問題にもつながるでしょう。エルサレムのアイヒマンにしても同じです。アイヒマンはただ命令に従っていただけだというようになっています。私自身が感じているのは、S21の虐殺者の中にも、かれらは、拒否することはできたのではないか、人を殺すことを拒否することはできたのではないかということです。実際に拒否をした人もいて、そのひとびとはS21から別のところに転勤をさせられました。
しかし、現在において彼らが命令を拒否せず、人を殺したことが、善であったか悪であったか、それを判定するのは難しいことですし、それをいま後悔しているから善だとか悪だとか、正当化をすることも難しいことだと思います。多分、かれらは後悔ということばを言うことは絶対にできませんし、また許しを求めることはできません。それは、クメール・ルージュの兵士たち皆について同じです。
一言、小林先生はクメール・ルージュについてご研究もなさっていますし、20年前からカンボジアの研究をしておられるので、よくご存知かと思いますが、技術的にいって、S21で働いていた人たちは、普通、治安部隊の兵士を表す「ノコバル」と言うことばを使っていませんでした。「サンテバル」と言っていました。すでにこの呼び方自体が、抹殺・虐殺のプロセスに入っているのです。
またS21のエリートたちには、別の名前がありました。それは「党の純粋な道具」という呼び名でした。このように大量虐殺においては、イデオロギーが大きく働きますし、また独自の言語が大きな役割を持っています。
ルワンダの虐殺の際にも「丘のラジオ」 から、「人を殺すように」という呼びかけが行われた特別なことばがありました。また同時にその大量虐殺のスピードも重要になってくるでしょう。
ユダヤ人の強制収容所の、殲滅が行われたのはわずか1年と少し、そしてカンボジアにおいては、最大の虐殺がおこなわれた期間は1年半です。ルワンダに至っては、5ヶ月ないし7ヶ月だったと思います。このように短い期間で180万人というひとびとが殺されたということは、ものすごい殺戮のスピードです。そして、人間存在、人間、私たちに似たひとびとなのですが、そのひとたちがそこまで極端にラディカルになった時、いったんそこまで過激になったひとびとを、もとに戻すことが果たして技術的にできるかどうか、私は疑わしく思います。
- 小林:
はい、ありがとうございます。S21という映画については、出演者と監督との関係について、さらに細かい質問がたくさん寄せられました。しかし、時間がありませんので、一旦S21の話を離れて、次の質問に行きたいと思います。
寄せていただいたコメントの中には、たくさんですね、S21の映画を見ながら、その問題を私たちの問題として考える意見が寄せられています。例えば、同じことを繰り返さないためには、何をすべきか、とか、平時・平和なときではなくて戦争の中に自分が入ったときにどのような行動ができるか、といったコメントです。で、関連して、一つ質問として、監督にお聞きしたいのは、ヒューマニティという話を監督は何回か口にされています。で、ポル・ポト時代の指導者たち、ポル・ポトにしてもキュー・サムファンにしても、みんなフランスへ留学して、当時の学問、知識、ナレッジとしてのものを修めた人たちです。で、はたしてそのヒューマニティの源泉というか、ポル・ポトたちが異文化の間を帰ってきて、得て、その実現をしようとしたもの、野蛮と文明という対比も監督はおっしゃられていましたが、その文明の中にも、何が一番大切なものか、ということを、この、自分たちの問題として考えて、こういう虐殺の悲劇とかですね、考えるときに、何か、コメントがあればお聞かせいただきたいと思います。
- パン監督:
長い質問をいただいてしまいました。確かに、革命のルーツについて考えるべきではないでしょうか。なぜ革命をするのか、それを考えるべきでしょう。私自身もなぜ自分が映画を作るのか、と考えます。革命を行うとき、それは正義を実現するためです。私が映画を作るのは、正義の不在・不正を告発するためです。全ての革命が、そうした出発点から始まっています。正義を実現するため、民主主義と自由を実現するためです。
問題は、その革命の後です。そして、他者の幸福を願いすぎると、自分の意図にもかかわらず、別の危険な方向に行ってしまいます。革命の後にはいつも、そうした方向に行ってしまう。しかし、現代の問題として、革命は今後も続けていくべきでしょう。現代は、革命を行うべき時期です。現在全てがバラ色でうまくいっているのではなく、革命が必要でしょう。また、今はイデオロギーが不在の時代になりましたが、イデオロギーがないために、非人間的な、過激なリベラリズムが力を振るうままになるという危険が起きています。このイデオロギーの不在もまた現代の問題でしょう。
革命のルーツに戻って、戦いを続けることが重要だと思うのです。しかし、一旦革命が実現をしたとき、他者の代わりに自分が他者に関しても決定を下すようになってしまった時、一定の謙虚さを持つことがその時には特に重要なのではないかと思います。他のものを生きさせる、他の生命や他の人生を尊重することがとても重要でしょう。
私自身、難しい時期を生き抜いてきましたけれども、幸福になる可能性があること、幸福が存在することのなかに、人生のモチベーションを私は見出しています。人生に対してポジティヴな見方をすべきではないでしょうか。人生は生きる価値がある、存在を続けるだけの価値がある、そうやってなるべく闘いを続けて、解決策を探す価値があると信じたいと思っています。そうしたことを早く学校教育の中で幼いときから教えるべきではないでしょうか。他人に対して寛容であることを教え、また、他人と共に生きることを小さいときから教えるべきでしょう。現在人々は共に生きる、という方向には動いていません。それぞれが自分のうちに閉じこもり、テレビやタブレットを前に一人でいる時間の方が多くなってきています。再び他者たちと共に生きることを教えるべきではないでしょうか。もちろんそうしたことを言うのは簡単で、実際に行うのは難しいことかもしれません。ただ、現在、人生のリズムが、共に生きることをむしろ崩壊させる方向に向かっているように見えます。
けれども絶望してはなりません。そうした、正しい方向に向かう努力を、一歩進んで二歩下がり、また三歩進んで二歩下がるという形で試行錯誤しながら行っていかなければならないと思います。このようにして良い方向に向かうその道程が肝心なのであって、闘争は繰り広げること自体が重要なのです。
- 小林:
ありがとうございました。では、時間的には最後の方の話題になりますが、映画の、ドキュメンタリーの映画についての質問が何個か寄せられています。で、その中でも一つは、同じ、同じというか、類似した主題を扱った「Act of Killing」というインドネシアの事件を扱った、そういう映画があります。その映画などについて、近年の、その、虐殺を扱う他の映画について、どう思われますか、という質問です。
- パン監督:
「Act of Killing」のジョシュア・オッペンハイマーの仕事は私もよく知っています。私の「S21」が、「Act of Killing」の大半を撮影するきっかけになったということも聞いています。ただ、ジョシュアがここにいればいろいろ言いますが、いないところでその話をするのは少しどうかと思うのです。私が、例えば個人的な理由で行けなかった領域において、ジョシュアは少し行き過ぎたところにまで行っているように思われます。ときには実体験をした者、虐殺を生き延びた当事者ではない方が物事は簡単になることがあります。私自身は、虐殺を目の当たりにし、あの時代を生きた当事者でありますから、ある種の領域においては、映像にすることができない部分があるのです。ただし同じ虐殺に関しても、異なる視線がもたらされるのはとても良いことです。「Act of Killing」について語るのであれば、あの映画を上映した上で、ここが好きだとか、ここはちょっと、とか、そういうふうなコメントの仕方をする方がよいでしょう。
私自身がどのようにドキュメンタリーを実践しているかを皆さんにご説明するために再びS21のあるシーンを取り上げてみましょう。つまりこのような虐殺をテーマにしたドキュメンタリーを作るとき、まず忍耐強いことがとても重要です。自分自身に対して、一つの心理的な手段を持たなければならない。あまり好きな言葉ではありませんが、道徳的な規則を自分に対して定めていなければならない。道徳的という言葉は嫌いですから、倫理的な規則を持っていなければならない、といった方が良いでしょうか。何か死にまつわる不吉なものや、また暴力、血、死などに強い衝撃を受けていると、撮った映像が覗き見趣味的なものになったり猥雑なものになったりする可能性があるのです。カメラのファインダーから何かを見るという行為自体、覗き見趣味に陥りがちです。ですからドキュメンタリーを撮るときはとても慎重でなければなりません。
この映画の幾つかのシークェンスの中で、私はカメラが回るのを止めたところがあります。なぜならばそれ以上撮影をしたとしたら、それを編集して使ってしまうだろう、そうすると間違いを犯すことになるだろうと思って、カメラを止めたシーンがあるのです。
それが自分の反射的な行為なのか、本能なのか、それとも私の周りにいる死者たちが、私が良い選択をするように助けてくれていたのかわかりませんけれども。そのシークェンスは、S21のなかで看守だった人が監房のなかにはいっていて、昔とした動作をするところです。もう少しで、自分にとって気分の悪いものになっていたでしょう。撮影をするときに私が自分で止めたのは、カメラと共に監房のなかに入っていくこと、カメラを持って看守についていくことでした。幸運なことに、私のカメラは監房のなかに看守と一緒に入りませんでした。しかし、あのシークェンス、あのショットの力学から考えると、看守について監房の内側にカメラが入っていくことはごく自然なことでした。
しかし私はなかには入らず、監房の入り口の外、別反対の側にとどまったのです。もしそこであと3歩前に行っていたら、あと1歩前に進んでいたとしたら、私のカメラは虐殺者の側に立つことになってしまったでしょう。そうするとおそらくその監房のなかに倒れていた死者=囚人を踏みつけて歩くことになってしまったでしょう。バリアの向こう側に私は行かなかったのです。その一歩が大きな違いです。何が私を引き止めたのか、それは本能的なものだったのか、私のなかにある何かだったのかわかりません。けれども、手持ちカメラでレンズを覗いているとき、これは撮れないと思うものがあるのです。
ドキュメンタリーとはレジスタンスの行為です。全てを撮影してはならない、全てを撮影することに対して、抵抗しなければならない。そうしてこそ、目の前で、カメラの前で起きていることに対して、正しくあれるのです。そして、センセーショナルなものがもたらす誘惑に負けてはなりません。覗き見趣味になってしまいます。
そうしたことうまく他の人に教えることができないのですけれども、若い映画作家に対し、ドキュメンタリーに関するアドバイスをすることがあります。それは「たくさん本を読みなさい」というアドバイスです。いろいろ映画を観るでしょうが、たくさん映画を見たからといって、良い映画作家になれるとは限らない。むしろ詩や哲学や作家たちの書いたものをたくさん読みなさいと勧めています。
それは、本をたくさん読み教養を持つことで、死者たちに対して尊重をすることができるようになりますし、消え去っていった人々を尊重することができるようになるからです。消え去った人々といっても、完全に消えてしまっているわけではない、記憶が残っていてまだそこにいます。記憶を尊重することが重要です。
そうしたことをよく言っています。ですから、映画のあのシーン、もしも虐殺者の側についていっていたとしたら、それは大きな失敗だったろうと思います。